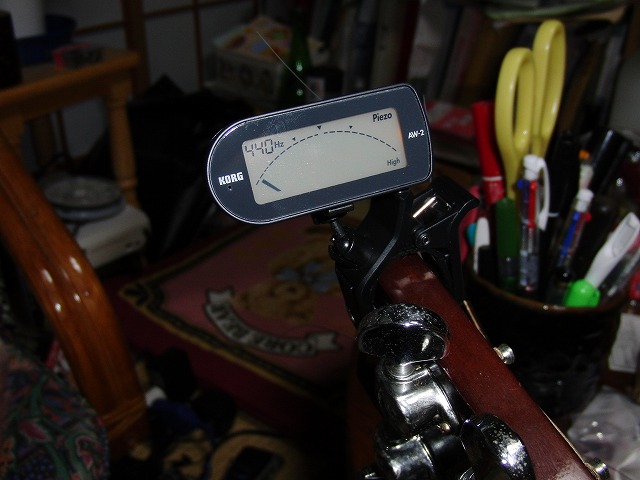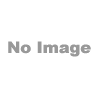屋根の上のアオサギ
通勤途中の道路の50メートルほど向こうに農作業小屋がある。スーッと通り過ぎてから小屋の屋根の上にいつもと違う違和感がある。アレッと思い後ろを見ると屋根の上には大型野鳥アオサギが1羽止まって周りを睥睨している。
屋根の上からエサを狙っているのだ。この地域(西仙北町土川)には春からアオサギが田圃に立っていてカエル、オタマジャクシ、ドジョウなどをエサにしている。
春先は早苗が植えたばかりだから田圃に立っているアオサギはかっこよかった。今、稲穂が実りはじめたので田圃に立つのは背の高いアオサギでも無理。そこで周囲の小川などでエサをとっているのだろう。
途中でUターンして写真を1枚。遠くで撮ったのでピンぼけだった。それでも後頭部へ黒い冠羽が垂れ下がっているのが見える。これはアオサギの特徴でもあるようだ。一本足で立っているのもご愛敬。それにしても、大きくしてみるとそれほどかっこいい鳥ではないぞ。
野鳥に興味を持った頃。40年ほど前のこと。中西梧桐さんの野鳥の本を読んだ。その中にアオサギを飼っていた人がくちばしで目を突かれたことを書いていた。なんてすごいんだアオサギは。と、思った。あの本はどこにいったんだろうなぁ。
なで肩の姿は妙に貧相な
アオサギ実はどう猛野鳥
学力とは
昨日から全国学力調査の結果でにぎやかだ。秋田県は小学校6年生全国1位。中学3年生全国2位と好成績を維持したと報じている。
まぁ、ボクは基本的にこの学力調査には反対の立場をとりたい。もしやるのならば抽出調査で十分だと考える。テストの点数だけを重視することの是非をもっと議論すべきだ。一喜一憂すべきではない。
と、ここまでは前置き。実は2009.8.25付の朝日新聞「科学五輪 理科好き生徒増やしたい」という社説が掲載された。
世界の高校生が競う国際科学オリンピックで、この夏日本代表が大活躍したことを書いている。
この中に「学力とは何か」を深く考えさせられる部分がある。少しピックアップすると次の通り
『過去の化学五輪で銅メダルをとったある高校生は、帰国直後の模擬試験で、60点満点で10点も取れなかったそうだ。日本の化学教育は本質的な理解を求めるより、知識を蓄えることに重点が置かれているためだろう。』
この辺に日本の学力の問題があると考えたいのだ。現在の日本では学力といえば知識をどれだけインプットして試験の時にどれだけアウトプットするかの能力が問われているのだ。
ただ知識を出すだけで持っている知識を総動員して考えることができない人が増えている。これは今回の学力調査でも「応用問題が弱い」傾向が出ていると報じている。知識ばかり追っかけているんだろう。まぁ、これはボク自身もそうだけど・・・。もっともあまり知識もないんですけどね。
そうそう、今朝(2009.8.28付)の朝日新聞天声人語にも免疫学者の多田富雄さんの話を引用している。孫引きであるが次のように書いている。
『医者がパソコンばかり眺めて、患者の顔を見て診察しない。数値に頼って患者の訴えを聞かない。多田さんによれば科学的根拠に基づく医療が行きすぎたゆえの問題らしい。(中略)最近、ある医学部を見学した人が驚いていた。「患者ロボット」を相手に問診の訓練をするのだという。なぜロボットなのかと聞くと、人との対話が得意でない学生もいますから、などと説明があったそうだ。』
実際に即して考えるあるいは行動する。そんなことができない。何が勉強だ。何が学力だ。何が医学部だと思えてしかたがない。
学力問題は「生きる力」そして「ひと」に結びついてくるような気がする。大切なのは点数ばかりじゃないんだ。本質は何かを見抜く力だと強く思う。でも、そんな力を本当に多くの国民が身につけたら「彼ら」は大変だろうなぁ。だから点数にしがみつくのかもしれない。
これにて本日のブログ終了。何だか理屈っぽくなってしまった。反省。